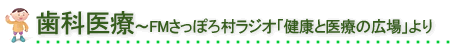トップページ>医療歯科〜FMさっぽろ村ラジオ「健康と医療の広場」より
| 勤医協中央病院が地域FM局に提供している健康番組「健康と医療の広場」に、2007年8月8日「歯科医療」について遠藤高弘(勤医協ふしこ歯科診療所歯科医師)がお話をしました。 内容についてご紹介いたします。また、 「聴く@勤医協」ブログでは、音声で聴くことができます。 |
|
◆ 最近、歯科疾患が全身に与える影響を耳にしますが、それはどのようなことなのでしょうか?
テレビコマーシャルでもごらんになると思いますが、口腔内には歯周病菌や詳しく分かっていない細菌も含め約300種類ほどの細菌が住み着いています。これらが歯を抜いたり歯みがきすることによって直接血管内に入ったり、誤嚥によって肺炎を起こす原因になったりしますし、細菌が出す毒素や好中球が細菌を破壊する時に分泌する化学物質などが、心臓・腎臓・胎児・糖尿病などに影響を及ぼすことが分かってきています。
日本では咀嚼学会と言うところで提唱した「ひみこの歯がいいぜ」という標語が有名です。それぞれ「肥満防止」「味覚の発達」「言葉がはっきり」「脳の活性化」「歯の病気予防」「癌予防」「胃腸のはたらきをよくする」「全力投球」と説明していますが、咀嚼がもたらす効用を分かりやすく説明しています。 とりわけ、よく噛むことに伴う唾液の効用は大変重要で、唾液の分泌不足に伴う口腔乾燥は高齢者に多く認められ、自浄作用不足による口臭の発生などにも関係します。 最近ダイエットのためのエクササイズがブームですが、よく噛むことだけで相当の効果がありますし、自動車免許の更新時の講義では、運転中の眠気防止にガムを噛むことがもっとも効果的とされています。 |
|
◆ どのように予防すればいいのでしょうか?
メタボリックシンドローム対策になぜか歯科は取り入れられませんでしたが、健康日本21で生活習慣病の一つに歯周病が取り上げられたように、日頃のセルフケアが大切です。
ただそれだけでは不十分で、私達専門家によるプロフェッショナルケアや噛み合わせを含めたチェック、それから地域単位で口腔の健康を推進するコミュニティケアが大事だと思っています。 日本の歯科検診制度は小学生までで、その後40歳から歯周病の節目検診が行われるまですっぽり抜け落ちますので、かかりつけの歯科医院を持つことをお勧めします。 一年間に一回でも定期的に歯科医院に受診する人の比率は、日本と欧米では5倍以上の違いがあります。 日本はフッ素の水道水添加は行われていませんが、フッ素添加の歯磨き剤や各種さまざまな口腔ケア製品が出ておりますので、歯科医院でアドバイスを受けられると良いと思います。 |
|
◆ すでに歯を失ってしまった方や高齢者の方は、どのようなことに注意すればいいのでしょうか?
野生の動物は自分の歯を失うことは捕食ができず死を意味しますが、人間は食物形態を加工できるため、歯を失ったあとでも長生きできます。入れ歯は人類最古の人工臓器と言われていますが、そのほかにもブリッジやインプラントなどの方法によって失った機能を回復することができます。
来年から後期高齢者制度がスタートし、政府の方針で在宅医療の推進が行われます。 歯科においても札幌市として在宅寝たきりの方に対する訪問事業があって、おそらく半分くらいの歯科医院は協力医となっています。しかし、実際には在宅の方やケアマネージャーの方から歯科的な要求はほとんど上がってこないのが実情です。 後期高齢者の医療機関の受診率は、医科が約60%、歯科は10%ちょっとという調査報告があり、お困りの方は札幌歯科医師会に申し込んでいただきたいと思います。 |
|
◆ 歯科では保険外の治療がありますが、保険が利くようにはならないのですか?
歯科においては医学上必要なものについても保険導入されていないものが数多くあります。1900年代はじめの頃、日本で健保組合などが作られていったときに、主に拠出側の経済的事情から、歯科の補綴(歯を失ったりしたときに行う術式、入れ歯やブリッジなど)は保険給付しないこととなっていました。また先進諸外国においても同様でした。
その後日本医師会とは異なる展開をしていったのですが、補綴領域においては同じ医療効果をもたらすものでもその術式や材料に大きく幅があるため、なかなか適切な保険導入が行われず、1950年ころ差額診療なども生まれました。 それも国民の批判を浴び、現在では一定のものは保険導入されたものの、金属床の入れ歯やインプラントや矯正、漂白などは保険外となっていますし、総医療費抑制の国家政策の中ではそれらの保険導入は困難となっています。 現在「保険でよい歯科医療を」という運動を、全国の歯科関連諸団体含め、医科・介護団体にも呼びかけて取り組んでいます。 ぜひ実現させたいものです。 |